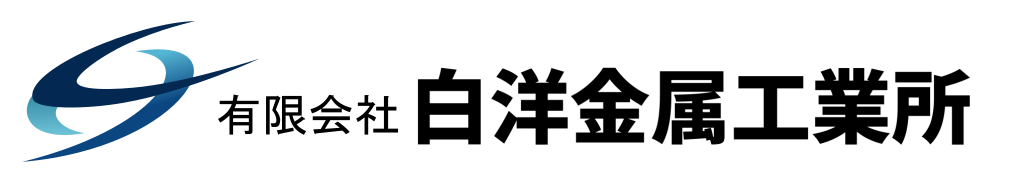クロメート処理って何なの?
クロメート処理のメカニズムを分かりやすく解説します

金属メッキの技術の一つであるクロメート処理。言葉自体は知っているけど、いまいちどんなものなのかを説明できる人は少ないのではないでしょうか。
偉そうな事を言っていますが、かく言う私も入社したころは、クロメート処理はヤマト運輸さんの配送方法の一つだと勘違いしていたくらいです。
この記事では
- クロメート処理の基本的な技術
- クロメートとクロムメッキの違い
- 三価と六価クロメートの違い
- クロメートに適した部品
などを、できるだけ専門用語を使わずに詳しく解説しています。
クロメート処理とは
クロメート処理は金属表面にクロメート皮膜を薄くはる技術の総称です。クロメート皮膜は六価クロムや三価クロムを含んだ「クロム酸」という特別な液体に金属を浸します。すると金属の表面とクロム酸が反応して、薄い「膜」ができます。 この膜がクロメート被膜であり、金属を守るバリアの役割をしてくれるのです。
クロメート処理をするのは鉄製品では主に亜鉛メッキをした部品です。金属を亜鉛メッキとクロメート被膜の二重のコーティングで守っています。
わざわざ二度手間とも言えるそんな処理をするのは、亜鉛メッキだけでは腐食しやすいため、亜鉛の腐食を防止する目的が大きいです。そして部品の耐食性(腐食や錆に耐える性質)を大きく向上させ、二重の被膜で製品の寿命を劇的に延ばせます。
クロメート処理をする理由
亜鉛メッキをコーティングして守る役割がクロメート処理にはある。その理由を深堀します。
金属の部品に亜鉛メッキだけをした状態では、風雨や湿度などの自然環境の影響を受けて、やがて亜鉛メッキに白サビが発生します。
そして、亜鉛メッキにできた白サビを放置しておくと、やがてメッキの下にある金属部分にも赤サビが発生してしまい、浸食された部品はボロボロに。
亜鉛メッキの上にクロメートの皮膜を張る事で、大気に直接触れない。守られる。だから、サビない。
その効果により金属製品の寿命が延び、長期間にわたってその性能を維持することが可能になります。
三価クロメートと六価クロメートの違い
代表的なクロメート処理には、三価クロメートと六価クロメートの2種類があります。この2つは別名で三価クロム、六価クロムと略すこともあります。
もともとあったのは六価クロメート処理です。六価クロムはその高い耐食性から多くの産業で利用されていますが、昨今では環境への影響が大きな懸念材料となっています。
六価クロムは、製造過程で有毒な物質を取り扱うので、特にEUや欧米などでは水質汚染や土壌汚染の原因となる物質として規制対象となっています。出来上がった製品には毒性はなく安全であることは長年の研究で証明されています。
ただし、現在は環境問題の観点から六価クロムから三価クロム、もしくは代替え技術に移行しつつあります。 それでも六価クロムには独自の強い耐久性などがあり、根強いニーズがあります。 六価の変わりとしてよく利用されている三価クロム処理は、環境に優しい選択肢として近年注目を集めています。この処理方法は三価クロムを使用して金属表面に耐食性の皮膜を形成します。特に三価クロムは有害性がないため、環境規制に適合しやすく、製造業界での採用が進んでいます。これにより、持続可能な製品開発が促進され、環境への負荷を軽減することが可能です。
六価クロメートの方が耐食・耐久性面で高いです。しかし、六価クロメートは環境への負荷を考慮して、海外では禁止されている国もあります。日本のメーカーでも規制しているところはありますが、部品によっては代替えできない性能の高さにより、現在も使われています。
六価クロメートの皮膜は自己修復性を持つため、外部からの傷や損傷に対しても高い耐久性を示します。
少しくらいの傷ならば皮膜が破損しても内部のクロムが溶出して、皮膜を修復してくれます。この特性により、金属製品は長期間にわたり腐食から保護され、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。
※三価クロムは自己修復性をもちませんが、耐食性は優れています
クロメート処理で色鮮やかな仕上がりに
亜鉛メッキした後にクロメート処理をすると、金属特有の美しい色の輝きがさらに出せます。
種類は豊富で
- 光沢クロメート
- 有色クロメート
- 黒色クロメート
- 緑色クロメート
などなど、実にさまざまな種類と色があり、ピンクや虹色なんてのも可能です。塗装したマットな仕上がりとは違い、元の金属の質感を活かした独自の色彩を表現できます。
クロメート処理の仕方によって、部品の用途に応じた美しい外観だけでなく、優れた耐食性を持たせられます。細かな出来上がりが選べるということは、パーツ毎に最適な処理が選択可能となり、様々な場面で利用されています。
光沢クロメートは主に美観を重視した用途に使用される一方で、有色クロメートは耐食性を重視した分野での利用が一般的です。これらの選択肢は、製品の機能性や外観に応じて最適な処理方法を選ぶための重要な要素となります。 クロメート処理は物理的な手段である塗装と比較して、金属の素材が持っている質感を活かせます。
クロメート処理とクロムメッキの違い
クロメート処理と名前が似ているので、この2つはよく混同されがちですが、まったく違った技術です。詳しくはまた別記事で深堀り致しますが、違いについてザックリ表にすると
クロメート処理とクロムメッキの違いまとめ
| 項目 | クロメート処理 | クロムメッキ |
| 目的 | 防錆性を高める | 装飾性や耐摩耗性を高める |
| 主なめっき | 亜鉛 | ニッケルクロム、硬質クロム |
| 厚さ | 非常に薄い | 薄い~厚い |
| 見た目 | 青みがかった銀白色や黒色の光沢 | 銀白色 |
| 用途 | ボルト、ナット、内部部品など防錆が必要な部品 | 車などの装飾部品、工具、金型部品など |
| 防錆性能 | 高い | 中程度(主目的ではない) |
| 耐摩耗性 | 低い | 高い |
上の表の用途をふまえて
- クロメート処理
車のボルトやナットを始めに様々な部品に使われています。部品自体は外から見えにくいですが、サビにくくして安全性を保っています。
- クロムメッキ
バイクのハンドルや車のバンパーなどのピカピカした金属部分によく使われているのが、見た目が美しい装飾クロムメッキです。硬質クロムメッキは硬さと摩耗性があり傷にも強いです。
安価に部品の耐久性を向上
クロメート処理は金属の表面に緻密な皮膜を形成することでサビから金属を守り、製品の寿命を延ばす効果があります。
色々な金属に付与できますが、全ての金属にクロメート処理が適しているわけではありません。部品の材質や使用環境、コストなどを総合的に考慮して、最適な表面処理方法を選ぶことが重要です。
もし、クロメート処理についてさらに詳しく知りたい場合は、お近くの専門業者に相談することをおすすめします。
弊社でもクロメート処理について無料相談ができます。クロメート処理の費用や納期について知りたい。などなど、些細な事でも構いません。下記のお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。